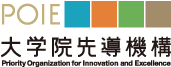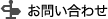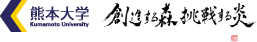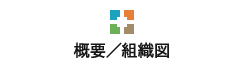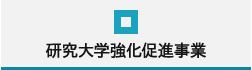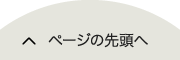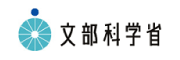拠点形成研究部門では、国際先端研究拠点、クロス・フロンティア研究推進事業、わかば研究推進事業の3つの支援を設け、プロジェクトの萌芽期から融合研究、世界最高水準の研究まで育成・支援体制を整備しています。
国際先端研究拠点(平成28年度 認定件数4件)
過去にグローバルCOEプログラムの採択を受けるなど、国際的に卓越した教育研究拠点を形成し世界をリードする人材育成を実施してきた実績を持ち、本学を代表する世界最高水準の先端的・先導的研究拠点を形成しています。支援期間は6年間、熊本大学中期目標・中期計画に照らした評価を行い、当該期間に合わせて支援を実施しました。
第4期中期計画・中期目標期間中は、同拠点を中心としたプロジェクトにおいて学際的研究や研究組織の充実、 多様な若手研究者の育成、共同利用・共同研究拠点の機能強化によってさらなる研究領域の拡大と高度化を図るための取組に対して支援します。
- 発⽣医学と幹細胞⽣物学の国際先端研究強化プロジェクト / リーダー:丹⽻ 仁史
- 国際先端ウイルス感染症研究Σプロジェクト / リーダー:上野 貴將
- 二次元ナノマテリアル先端研究形成プロジェクト / リーダー:伊田進太郎
- 先進軽金属材料の教育研究プロジェクト / リーダー:河村 能人
クロス・フロンティア研究推進事業(令和4年度より開始)
これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換しうると期待される分野横断型グループの基礎研究を支援することで、大学全体の学術水準の向上や若手研究者の育成につながる研究領域の創成を目指します。
| プロジェクト名 | 研究代表者 |
|---|---|
|
半導体微細加工技術を活用した温度デジタルツインの開発 |
有馬 勇一郎 |
|
細胞内半導体チップを使って体の深部温度を測る |
大川 猛 |
|
半導体 with ヘルスケア:軟口蓋AI画像解析を用いた食道がん早期発見のためのPoint-of-Care装置の開発 |
田中 靖人 |
|
半導体加工技術を応用した細胞形状加工技術を基盤とするインビトロ腫瘍モデル形成と病理解明への応用 |
中島 雄太 |
|
尿中修飾ヌクレオシド測定によるスポーツ疲労の可視化と競技クオリティとの関連 |
永芳 友 |
|
考古学における種実・昆虫圧痕分類のためのAIモデルの開発 |
メンドンサ ドスサントス イスラエル |
|
GIS技術に基づく蚊の生息地と植物の生活環境相関モデルの社会実装への応用研究 |
米島 万有子 |
| プロジェクト名 | 研究代表者 |
|---|---|
|
デジタル画像解析と数値流体計算による生体微小環境動態学の構築 |
有馬 勇一郎 |
|
国際規格化を念頭においた里山ランドスケープの評価法の確立による過疎化地域の活性化 |
澤 進一郎 |
|
医と工のタッグで解き明かす“目に見えない”フォースの生物学 |
諸石 寿朗 |
|
ハンセン病・HIV/AIDS・Covid-19の事例を踏まえた感染症に関する科学コミュニケーションの研究 |
八幡 英幸 |
|
臓器老化連関の基本原理「脳内キメリズム」の解明 |
滝澤 仁 |
|
AI天然物創薬による革新的医農薬シーズ探索 |
人羅 勇気 |
|
多剤耐性乳癌における核上皮成長因子受容体の視覚化と定量化 |
LEE RUDA |
|
血中を循環する腫瘍細胞ならびに癌関連線維芽細胞の統合的理解 |
北村 裕介 |
わかば研究推進事業(令和6年度より開始)
若手研究者を対象に既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な研究を支援することで、若手研究者の育成と本学のプレゼンスの向上を目指します。
| プロジェクト名 | 研究代表者 |
|---|---|
|
流体的左右非対称性の可視化・測定・操作と再構築 |
淺井 理恵子 |
|
老化細胞のエピゲノム状態を規定する転写因子の探索 |
衞藤 貫 |
|
認知症予防のための新たなバイオマーカーの確立と評価 |
梶谷 直人 |
|
動的電子状態に基づいた高性能極性材料創製の新学理 |
関根 良博 |
|
「ヒストン模倣」の作動原理および生理的意義の解明 |
髙島 謙 |
|
生理的・臨床応用可能なヒトマクロファージ増幅法の確立 |
髙橋 尚史 |
|
酪酸菌を用いた腸管免疫を標的とする革新的がん治療法の開発 |
冨田 雄介 |
|
酸素イオン伝導ナノシートの合成と機能開拓 |
畠山 一翔 |
|
ダウン症遺伝子による血管機能調節に基づく動脈硬化抑制の分子機構解明と創薬応用 |
舟﨑 慎太郎 |
|
系譜特異的なマクロファージが心血管系を老化に導く制御機構の解明 |
劉 孟佳 |
みらい・めばえ研究推進事業(平成29~令和5年度)
既に高い評価を受けている研究者が中心となるグループの研究で、次世代の本学を代表する世界トップレベルの研究領域として発展させるとともに、当該領域をけん引するリーダーの育成・輩出することを目指す研究拠点を「みらい研究推進事業」として支援します。また、学術の既成概念や方向を大きく変革・転換しうる大胆で挑戦的な研究を、将来の本学を代表しうる研究を活性化することを目的に「めばえ研究推進事業」として支援します。
みらい研究推進事業(平成29~令和3年度)
| プロジェクト名 | 研究代表者 |
|---|---|
|
熊本藩関係資料群の総合的解析による日本近世史研究拠点の形成 |
稲葉 継陽 |
|
ミトコンドリア恒常性制御と変容の分⼦基盤解明 |
尾池 雄一 |
|
熊大ライブラリーを基盤とした革新的医薬品シーズの同定と製剤化 |
杉本 幸彦 |
|
代謝リプログラミングを基盤とした疾患の病態解明と新規治療法の開発 |
馬場 秀夫 |
|
二次元物質に基づいた機能材料の創製およびその応用展開 |
速水 真也 |
|
ヒトT細胞白血病ウイルス1型の病原性発現機構解明と新規治療法開発 |
松岡 雅雄 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
LINE-1解析を起点とした癌と精神疾患の病態解明 |
馬場 秀夫 |
|
ユニーク・ライブラリーを活用した次世代型創薬研究 |
杉本 幸彦 |
|
熊本藩資料群の総合的解析による日本近世史研究拠点の形成 |
稲葉 継陽 |
|
多階層的視点による老化・健康寿命を制御する機構の解明 |
富澤 一仁 |
|
基礎科学研究を基盤とした生物資源開発と農薬開発、農水産業展開 |
澤 進一郎 |
|
2D-材料を基材に用いた機能材料の創製およびその応用展開 |
伊田 進太郎 |
|
ATLをモデルとした慢性炎症・炎症ストレスによる白血病化メカニズムの解明 |
松岡 雅雄 |
|
材料界⾯アーキテクチャーによる⾰新的機能を有する構造材料・機能材料創製研究 |
連川 貞弘 |
めばえ研究推進事業(平成29年度より開始)
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
電力・交通システムの相互依存性に着目した技術革新が災害時脆弱性に及ぼす影響 |
安藤 宏恵 |
|
スピネル型フェライト中のカチオン不規則配列が酸化反応活性に与える影響の解明 |
猪股 雄介 |
|
近代ドイツにおける「詩人と思想家の時代」の批判的検討 |
益 敏郎 |
|
マルチオミクスデータ解析のためのプラットフォームの開発 |
衞藤 貫 |
|
ミトコンドリア恒常性維持変容を基盤とする臓器老化機構の解明とその制御 |
門松 毅 |
|
楽器演奏支援ロボットによる教育・福祉への展開 |
上瀧 剛 |
|
Radiogenomicsによる消化器癌の革新的新規治療戦略の確立 |
小澄 敬祐 |
|
テーラーメイド再生医療に向けた組織内血管網の新しい設計手法の考案 |
小俣 誠二 |
|
2次元金属有機フレームワーク(MOF)超構造の電子物性および電気化学特性 |
ZHANG ZHONGYUE |
|
水素結合集積化による極性スイッチング分子の創出 |
関根 良博 |
|
抗腫瘍効果を発揮する酪酸菌の免疫学的作用機序の解明と新たながん治療法の開発 |
冨田 雄介 |
|
生物種横断的な受精能獲得制御因子を標的とした生殖クライシスの課題解決 |
中尾 聡宏 |
|
修飾ヌクレオシド測定を基盤とする羊水メタボロミクスで挑む感染関連超早産の病態解明 |
永芳 友 |
|
子宮外胎仔培養が切り拓く臓器発生の統御メカニズム |
仁田 暁大 |
|
エポキシカーボンナノシートを用いた高性能バリア膜の開発 |
畠山 一翔 |
|
数的染色体異常の新規モデルを用いた造血幹細胞の制御とがん化の分子基盤解析 |
花谷 信介 |
|
光操作でやる気スイッチを ON にする |
人羅 菜津子 |
|
難治性抗酸菌感染症に対するマクロファージをターゲットとした新たな治療戦略 |
矢野 浩夢 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
地球科学分野での深層学習の適用における諸問題の明確化と解決策の提案 |
石田 桂 |
|
プロトンによる有機結晶の革新的バンド充填制御法の開拓と新電子機能創出 |
上田 顕 |
|
老化細胞における分泌装置ゴルジ体の断片化の意義の解明 |
衞藤 貫 |
|
複数の観測周期・制御周期が混在する制御システムに対するマルチレート制御理論の展開 |
岡島 寛 |
|
ミトコンドリア恒常性維持変容を基盤とする臓器老化機構の解明とその制御 |
門松 毅 |
|
マルチオミクスによる多発性骨髄腫の最適な治療法の確立 |
河野 和 |
|
気圧情報を脳温に変換する生体システムの全容解明 |
倉内 祐樹 |
|
迅速な自然免疫応答を司るクロマチン高次構造クラウチングスタート仮説の検証 |
黒滝 大翼 |
|
自然免疫と代謝を標的とした次世代型抗ウイルス治療・予防薬の開発 |
幸脇 貴久 |
|
植物根の内生共生と寄生における根圏微生物群ダイナミックス |
TSAI YI LUN |
|
野生型ATTRアミロイドーシスの加齢依存的な発症機構に基づいたバイオマーカー同定とその定量法開発 |
佐藤 卓史 |
|
電子ドナーアクセプター分子の配列制御による極性機能発現の創出 |
関根 良博 |
|
患者由来腎臓オルガノイドを用いた変異タンパク質の動態解明と制御 |
谷川 俊祐 |
|
マルチオミクス解析による膵β細胞加齢性変容機構の解明 |
津山 友德 |
|
「教育学のメタ理論体系」に基づく「役に立つ教育学」の実装 |
苫野 一徳 |
|
酪酸菌による免疫システムを介した抗腫瘍効果の機序解明と新たながん治療法の開発 |
冨田 雄介 |
|
数的染色体異常の新規モデルを用いた造血幹細胞の制御とがん化の分子基盤解析 |
白 潔 |
|
エポキシカーボンナノシートを前駆体とする、機能性2次元ナノカーボン材料の開発 |
畠山 一翔 |
|
穿孔性腹膜炎における腹腔内GATA6陽性マクロファージの役割 |
本田 正樹 |
|
「先天性」好中球減少症の「後天的」発症機構 |
森嶋 達也 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
IoT/AI指向のシステム設計基盤技術に関する研究 |
尼崎 太樹 |
|
染色体を覆うRNAは染色体の動態を制御するか? |
井手上 賢 |
|
キラルな結晶構造をもつ金属酸化物を用いた分子不斉認識 |
猪股 雄介 |
|
粘膜ワクチン開発に向けたM細胞トランスサイトーシス介在分子の同定 |
岸本 直樹 |
|
核酸の自発的鎖交換反応を利用した高感度腫瘍細胞の検出 |
北村 裕介 |
|
遺伝子改変マウスを用いた炎症記憶細胞の可視化技術の開発 |
古賀 友紹 |
|
地球コア圧力条件下における液体鉄合金の音速測定への挑戦 |
中島 陽一 |
|
「性特異的なエピゲノム状態の確立のゆらぎ仮説」に基づく性別違和のバイオマーカー開発 |
仲地 ゆたか |
|
ゲノム安定性維持に関わる酵素反応の精密解析 |
中村 照也 |
|
血管とリンパ管のネットワーク独立性維持機構を標的とした革新的リンパ浮腫創薬 |
馬場 理也 |
|
脳活動の外来的誘導による神経回路の再建 |
水野 秀信 |
|
ストレス耐性に不可欠な造血幹細胞維持機構の解析 |
森井 真理子 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
染色体を覆うRNAは染色体の動態を制御するか? |
井手上 賢 |
|
一種類の分子で創る究極の有機超伝導体 |
上田 顕 |
|
モデル誤差抑制補償器のセンシング環境に関する研究深耕 |
岡島 寛 |
|
細菌の必須酵素SpoTの阻害による新規抗菌剤の探索 |
小野 勝彦 |
|
ES細胞から造血幹細胞への試験管内分化誘導法の開発 |
古賀 沙緒里 |
|
触質感の収集/分類/生成システムの構築 |
嵯峨 智 |
|
地球コア圧力条件下における液体鉄合金の音速測定への挑戦 |
中島 陽一 |
|
ゲノム安定性維持に関わる酵素反応の精密解析 |
中村 照也 |
|
ヒト脳の理解を目指した脳回脳溝形成メカニズムの解明 |
畠山 淳 |
|
「舐める」ワクチンの開発 |
前田 仁志 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
ミトコンドリアタンパクの翻訳後修飾を標的とした細胞保護療法の開発 |
有馬 勇一郎 |
|
抗体医薬による神経変性疾患治療のための脳関門透過技術の開発 |
伊藤 慎悟 |
|
リボソーム解析による多能性幹細胞の樹立機構の解明 |
伊藤 尚文 |
|
希少疾患治療を目指した次世代型核酸医薬の開発 |
勝田 陽介 |
|
性格形成メカニズムの解明 |
倉内 祐樹 |
|
神経回路を選択的に刺激して幸福感を生み出す-マウスでの検討- |
竹本 誠 |
|
ゲノム安定性維持に関わる酵素反応の精密解析 |
中村 照也 |
|
腸内細菌シグナルによって制御される多臓器連関造血応答の解明 |
林 慶和 |
|
二次元材料複合構造における表面現象の制御 |
原 正大 |
|
血中循環がん細胞と血管内皮細胞との相互作用に基づいた転移臓器親和性の解明と転移抑制法の開発 |
村松 昌 |
|
オルガネラ間接触領域を形成する因子の同定と機能解析 |
山本 真寿 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
飲み薬で投与可能なインスリン製剤の開発 |
伊藤 慎悟 |
|
乳酸菌による腫瘍除去法の開発 |
伊藤 尚文 |
|
未知物質の濃度をはかる |
大平 慎一 |
|
アントラセン修飾DNAの光二量化を利用した細胞の時空間特異的観察及び操作 |
井原 敏博 |
|
統合失調症発症に至る大脳皮質GABAニューロン機能破綻の臨界期を探る |
江角 重行 |
|
がん糖鎖を標的としたがん転移抑制剤の開発 |
大坪 和明 |
|
バイオマテリアル微粒子によるマクロファージの活性化と新規がん治療法への応用 |
中島 雄太 |
|
地球中心コア圧力下での液体鉄合金の物性解明 |
中島 陽一 |
|
あらゆる素材に生命体の表面構造を創製する加工技術〜市場へのインパクトをめざして〜 |
中西 義孝 |
|
新奇化合物で構成されるアンモニア燃焼分解触媒の開発 |
日隈 聡士 |
|
骨髄移植の安定供給を目指したヒト造血幹細胞の自己複製を誘導できるリガンドの同定 |
増田 豪 |
|
健康長寿の向上を企図したバイオミメティクDDSの創製とサルコペニア治療への応用 |
丸山 徹 |
|
倍数性進化・ダウン症モデル解析に基づくがん・生活習慣病の発症機序解明と創薬応用 |
南 敬 |
|
Hippo 細胞内シグナルを標的としたがん免疫療法の開発 |
諸石 寿朗 |
|
エクソソームによる肺腺癌の悪性化機構の解明と診断技術の開発 |
山口 知也 |
|
革新的な神経変性疾患の定量的画像診断を実現するMRI位相画像技術の研究と検証 |
米田 哲也 |
| プロジェクト名 | 研究者 |
|---|---|
|
人類の新様態としての認知症者のコミュニケーションメカニズムの解明 |
石原 明子 |
|
がん糖鎖を標的としたがん転移抑制剤の開発 |
大坪 和明 |
|
電場と膜透過に基づく溶存イオン抽出による希少元素回収・分離精製技術の確立 |
大平 慎一 |
|
皮膚腫瘍の融合遺伝子の探索 |
神人 正寿 |
|
黄砂・PM2.5の急性心筋梗塞・心原性心停止に対する影響と高感受性集団の同定 |
小島 淳 |
|
極限的時空間反応場における光機能物質の物性解明 |
小澄 大輔 |
|
細菌のシステイン合成経路を標的とした新規抗菌薬の探索と臨床応用を目指した基礎研究 |
澤 智裕 |
|
植物の葉緑体は「壁」を持つのか? |
高野 博嘉 |
|
あらゆる素材に生命体の表面構造を創製する加工技術 |
中西 義孝 |
|
細胞のみで機能的3次元化血管を構築する再生医療技術開発 |
野口 亮 |
|
歯周病菌感染はアルツハイマー病の介護負担を増やすか? |
長谷川 雄 |
|
霊長類の大脳皮質拡大化を支えるメカニズム |
畠山 淳 |
|
ムライト型結晶構造体を基軸とするアンモニア燃焼触媒の物質設計 |
日隈 聡士 |
|
骨髄移植の安定供給を目指したヒト造血幹細胞の自己複製を誘導できるリガンドの同定 |
増田 豪 |
|
ホウ素と希土類元素の複合添加によるZr基およびHf基高温型形状記憶合金の開発 |
松田 光弘 |
|
がん細胞でのROR1による生体膜ダイナミクス制御機構の解明 |
山口 知也 |
|
新型ナノカーボンの合成法開発による機能開拓の加速 |
横井 裕之 |
|
臨床用MRIで実現可能な神経変性疾患の発症前診断を目指した白質ミエリンの定量化技術の研究・開発 |
米田 哲也 |
アマビエ研究推進事業(令和2~3年度)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の脅威は、世界中で拡大しており、数年単位の長期戦も予想されています。
現代社会における人類最大の課題と言っても過言ではない新型コロナウイルスに関するさまざまな課題に対して、熊本大学は英知を集結させ解決策を模索します。令和2年7月、新型コロナウイルスの課題解決を目指した熊本大学の研究を支援する「アマビエ研究推進事業」がスタートしました。
新型コロナウイルスのしくみや感染を防ぐ方法、新型コロナウイルスによって変化を求められている社会のあり方や教育についての研究を推進し、研究大学として研究成果をいち早く社会に還元して参ります。